2025年10月号(174号)-2
長年の仕事の収穫期
■かごしま有機生産組合(鹿児島県鹿児島市)■
1984年に設立された日本最大の有機農業生産者団体。新規就農者の育成にも力を入れており、直営農場での研修や行政と提携し、生産者支援センターも立ち上げた。よつ葉とのお付き合いも長く、じゃが芋、人参、さつま芋といった根菜類はよつ葉で欠かすことができません。

山脇さんご夫妻
子どもたちが産まれたとき、農薬散布をした手で授乳をさせることに不安を感じたのが20代半ば。有機農業への転換点でした。その子どもたちも独立し、夫と二人の暮らしに戻りつつあります。農業技術も未熟なまま、手探りでつくり続けたさつま芋や人参も30数年を経て、収量も品質も安定したものになってきました。三歩進んで二歩下がる。ジェットコースターのような農業人生だったと、今は苦笑いしながら振り返ります。
この長い間、農業を生業(なりわい)にしてこられたのも、食べてくださるお客さまと、野菜をお客さまの元に届けてくれた各団体のスタッフの力と、私たち後輩に知る限りの失敗と技術をつないでくださった先人たちの努力の積み重ねと、不安定な日常を受け入れ、共にしのいでくれた子どもたちのおかげだったと思います。
60代半ばの私たち夫婦、来る引退前にやらなければならないことと、残りの時間に限りがあることをひしひしと感じます。失敗と技術はワンセット、次世代にそれを伝え、育てた畑を引き継がなければなりません。幸い、山脇農園は長女、長女の婿、三女が仕事に通ってきてくれています。今、誰がやっても正確に結果を出せる詳細な作物の栽培レシピを作成、情報共有の途中です。数年後には私たちが現場を離れても困ることはなくなるでしょう。むしろ、若い人のアイデアと体力に助けられ、私たち夫婦はいま、長年の仕事の収穫期を迎えているのかもしれません。そんな山脇農園から若者とともにつくった、今年のさつま芋をお届けします。間もなく、人参やレタスも出番を迎えます。皆さま、どうぞ安心してお召し上がりください。
(山脇紀子)
地域の熱い思いで設立
■山国さきがけセンター(京都府京都市)■
納豆発祥の地の一つといわれる京都市右京区京北山国地区で、地域の農家、自社で栽培した米や大豆を使った納豆もちなど、地域の郷土食として親しまれてきた商品をつくる。農地の保全と、第6次産業化を推進し、地産地消を進める。
お店:
京都市右京区京北塔町宮ノ前23


スタッフの皆さん
(後列真ん中が河原林さん)
京北山国地区は京都市中心部から30㎞、車で約1時間、周囲を山に囲まれ上桂川が流れる、自然豊かなところです。南北朝時代には北朝初代天皇光厳天皇が上皇になってから、戦乱を避け山国に来て、常照皇寺を開山しました。今も地域の人々から桜の名所のお寺として愛されています。地域ではその折に納豆が伝承されたと伝えられ、関西における納豆発祥の地として受け継がれています。
2001年、地域の有志の方々が出資し、高齢化が原因の後継者不足による耕作放棄地の解消、地域の伝統食文化の継承を目的に設立しました。農薬や化学肥料をなるべく使わないで地元で原材料を生産し手づくりにこだわり、地域の農地の保全と6次産業化を推進、地産地消を進めています。
山国さきがけセンターで栽培している大豆を使った「山国納豆」や納豆を餅につき込んだ「納豆もち」、納豆を餅で包み込んだ「あみがさ納豆もち」を製造販売しています。「あみがさ納豆もち」は昔は顔ぐらいの大きさで、お正月、三が日に食べていました。硬くなれば火にあぶって、その香ばしさを楽しみました。女性にとってはこの3日間だけが休息日でもあったようです。いぐさやわらで編んだ笠に似ていることから「あみがさもち」と名付けました。ぜひ、一度食べていただきたいです。秋から春にかけては、地域で採れるよもぎや山椒の粉を餅につき込んだお餅もつくっています。
地域の熱い思いで設立した山国さきがけセンター。これからも地域の期待に応えつつ、多くのお客さまに喜んでいただける商品づくりに従業員一同、励んでいきたいと思っています。
(河原林 勝)
わたしのおススメ
『フッ素の社会史』
天笠 啓祐 著
志智裕司(ひこばえ)
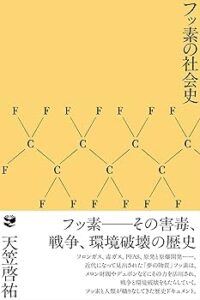
「フッ素化合物の歩みは、戦争と環境汚染、健康破壊の歴史である」という一文から始まる本書は、フッ素化合物の開発に至る経緯やフッ素を巡る技術が果たしてきた役割、その恐ろしさなどを歴史的に見た本です。
フッ素と聞いて一番はじめに頭に浮かんだのが、近年、人体汚染物質として大きく取り上げられているPFAS(有機フッ素化合物)です。環境や食物連鎖を通じて人の健康に影響を及ぼす可能性が指摘され、農林水産省は優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のひとつとして食品中の含有実績などの情報を収集しています。
有機フッ素化合物は核兵器開発中に生まれた、戦争がもたらした技術です。扱いが難しいが、いったん加工してしまうと非常に安定する性質を持ちます。熱や酸、アルカリ、有機溶剤などに強く、電気を絶縁し摩擦も小さいなど、優れた性能を発揮してさまざまな使用用途が開けます。身近なところで、マウンテンパーカーの撥水加工や、フライパンのテフロン加工などに使われています。他にも環境汚染物質の代表格、オゾン層破壊をもたらしたフロンガスや、毒ガス兵器として有名なサリン、さらに農薬や殺虫剤、抗がん剤などの薬剤、プラスチック、フッ素樹脂、半導体工場における洗浄剤など、ありとあらゆるところで使用されています。
「夢の物質」と呼ばれる有機フッ素化合物が、私たちの生活に少なくない恩恵をもたらしたことは、否定できません。一方で、工場や農薬、産業廃棄物などから流出し、マイクロプラスチックの海洋汚染や、水道水の汚染などで巡りめぐって食品や飲料水となって私たちの食卓に出回っている状況です。約1万種類あると言われるPFASのうち、現在日本では3種類しか規制されていません。その影響について、早急に調査して有効な規制を施すことが必要だと感じました。
フッ素汚染が広がった過程や、関連する企業、起きた訴訟などの詳細が記されています。ぜひ一度読んでいただきたいです。
